|
|
|
| |
| |
 |
| |
| |
| |
様々な国籍の外国人市民が増加し定住化が進む中、外国人市民が
地域住民との交流を深め、コミュニティ活動へ参加・参画できる
ようにするための環境づくりが必要となっていますが、日本語教
室は、外国人市民の日本語学習支援にとどまらず地域住民との交
流の場となっています。
地域日本語教室ボランティアの養成のために、主にこれからボ
ランティア活動を始めようと考えている人を対象とした全5回の
講座を開催しました。 |
|
| |
| |
| |
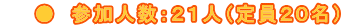 |
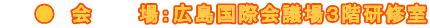 |
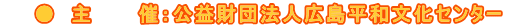 |
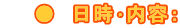 |
| 回 |
日 時 |
内 容 |
講 師 |
| 1 |
2月11日 土曜日
14:00~16:00 |
「日本語教室ってどんなところ?」
日本語ボランティア体験談
日本語学習体験談 |
竹内 由美子・板野 明子
(IVC国際ボランティアクラブ)
光原 鈴江・濱崎 デクスター・
ラーナ ディーパック シンガ・
ウィリアム バー
(ひろしま日本語教室) |
| 2 |
2月15日 水曜日
18:00~20:00 |
「日本語学習支援の基礎1」
地域の日本語教室の役割
国語と日本語
やさしい日本語 |
三島 佳代子
(ヒューマンアカデミー広島校
日本語教師養成講座講師) |
| 3 |
2月22日 水曜日
18:00~20:00 |
「日本語学習支援の基礎2」
美しい日本語
文化、習慣の違い
ペアワーク
日本語の基礎知識 |
三島 佳代子
(ヒューマンアカデミー広島校
日本語教師養成講座講師) |
| 4 |
3月 1日 水曜日
18:00~20:00 |
「日本語学習支援の基礎3」
日本にいる外国人
グループワーク
日本語の基礎知識 |
三島 佳代子
(ヒューマンアカデミー広島校
日本語教師養成講座講師) |
| 5 |
3月 8日 水曜日
18:00~20:00 |
日本語教室の紹介・交流会 |
光原 鈴江
(ひろしま日本語教室)
新谷 友代
(日本語学習会)
佐藤 雅子
(はるかぜ日本語ボランティア)
北川 正義
(にほんごくらぶ) |
|
| |
全5回の講座全ての回において、8割を超える出席率で、受講者は熱心に
日本語ボランティア活動の基礎を学びました。 |
|
| |
| |
| |
|
第1回では、昨年、当講座を受講し、日本語ボランティア活動を始め
られた、竹内 由美子さんのお話と、新たにボランティアを迎えられた板野 明子さんのお話を聞き、日本語ボランティア活動の面白さや難しさまたうれしかったエピソードなどを聞きました。続いて、日本語教室で日本語を勉強している、濱崎 デクスターさん、ラーナ ディーパックシンガさん、ウィリアム バーさんの日本語学習体験談を、光原 鈴江さんによるインタビューを通して聞きました。日本語教室で活動しているボランティアとそこで日本語を学ぶ学習者の双方の話を聞くことで、日本語教室がどのようなところで、どういった方が活動しているのかということを具体的に知る機会となりました。 |
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
第2回からは、日本語教師養成講座講師の傍ら、地域日本語教室のボランティア活動にも取り組んでおられる三島 佳代子先生の講義が始まりました。地域の日本語教室の役割について、意見交換を交えながら確認した後、「やさしい日本語」について学びました。震災の事例を通して外国人にとって、わかりやすい日本語で伝えることの大切さを学び、実際に「やさしい日本語」に言い換える練習も行いました。 |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
第3回は、引き続き三島先生による講義で、美しい日本語を話す意識を持ちながら正しい発音で日本語を話すことの大切さを学び、発声練習から始まりました。続いて、文化や習慣の違いについて、実際に日本語教室であった事例をもとに、グループに分かれて話し合いました。ペアワークでは、相手の話を聞く傾聴の練習をしました。日本語ボランティアにとって「聞き上手」になることの大切さを学びました。さらに、動詞のグループ分けなど日本語学習の基礎に触れ、日本語と国語の違いを確認しました。 |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
第4回は、三島先生による最後の講義になりました。発声練習でウォーミングアップを行った後、日本に住む外国人の状況について学びました。さまざまなバックグラウンドを持った方がいることを学んだ後、グループでケーススタディーを行いました。日本語教室に学習者が来られたことを想定し、どのように対応するかについて話し合い、すぐに実践できるようなさまざまな工夫や対応の仕方について意見交換をしました。後半は、日本語学習の基礎の続きとして、動詞と形容詞と助詞についての基礎を学んだ後、グループに分かれて、絵カードを使った実践的な学習支援の練習をしました。 |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
最終回の第5回では、ボランティアを募集している日本語教室の代表者が集まり、教室紹介をしました。グループに分かれて、それぞれの教室の状況やボランティア活動について、直接話をすることで、実際の活動内容や雰囲気などを知る機会となりました。希望調査では、教室を見学したいという回答が多く寄せられ、日本語ボランティア活動を始める一歩を踏み出すきっかけとなっていました。 |
|
|
|
|
| |
| |
|
| |
| |
| |

