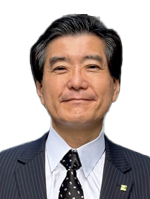たに しろう
谷 史郎
広島平和文化センター 副理事長
被爆・戦後80周年を迎える2025年の平和首長会議国内加盟都市会議総会が、1月16・17日、東京都武蔵野(むさしの)市で、100都市の参加をいただき、開催された。
1日目は、武蔵野市の企画による「ピースフロム武蔵野」が催された。 ここでは、戦争体験を如何に次世代に伝えるかに焦点が当てられることになった。
こどもたちの素晴らしい吹奏楽から始まり、4名の戦争体験者・被爆者からのメッセージ映像「戦争の記憶を平和な未来につなげるために」が放映された。 それにより、当時市にあった有数の飛行機メーカー・中島(なかじま)製作所が9回に及ぶ空襲を受け、多くの市民の犠牲があったこと、また、戦後広島・長崎の被爆者が武蔵野市民となり「武蔵野けやき会」を結成、啓発活動を行ってきたことなどが示された。 なお、100名を超えた同会の被爆者も現在30名を切り、活動の中心は2・3世に移りつつあるとのことである。 また、写真家で、武蔵野市民の大石芳野(おおいし よしの)さんは、講演「戦禍をこえて」で、様々な地での戦争を体験された方の悲劇を、写真を通してリアルに伝えた。
 2日目の取組報告では、多た摩ま地域の26市全てが加盟する「平和首長会議東京都多摩地域平和ネットワーク」から、各市の高・大学生1名ずつにより構成される「(仮称)多摩地域平和ユース」の広島への派遣と、2026年2月に多摩市で開催される「(仮称)平和サミット」でのユースによる政策提言発表などの予定が示された。
また、福岡県古賀(こが)市からは、絵本「中村哲(なかむら てつ)物語」の制作・学習や長崎・広島・知覧(ちらん)への修学旅行などを通じた追体験の重要性、愛知県大府(おおぶ)市からは、沖縄や被爆地への中学生平和大使の派遣、京都市からは、平和の尊さを見つめ直す「平和文化月間」の取組や意義などについて、発表が行われた。
2日目の取組報告では、多た摩ま地域の26市全てが加盟する「平和首長会議東京都多摩地域平和ネットワーク」から、各市の高・大学生1名ずつにより構成される「(仮称)多摩地域平和ユース」の広島への派遣と、2026年2月に多摩市で開催される「(仮称)平和サミット」でのユースによる政策提言発表などの予定が示された。
また、福岡県古賀(こが)市からは、絵本「中村哲(なかむら てつ)物語」の制作・学習や長崎・広島・知覧(ちらん)への修学旅行などを通じた追体験の重要性、愛知県大府(おおぶ)市からは、沖縄や被爆地への中学生平和大使の派遣、京都市からは、平和の尊さを見つめ直す「平和文化月間」の取組や意義などについて、発表が行われた。
その後、私から、「加盟都市の『平和に関する取組』に対する支援方策」特に若い世代への平和学習について、以下5点を説明した。
会議での主な議論としては、主催者の小美濃(おみの)武蔵野市長から、「これからは、様々な手法を使って、若い世代に戦争についてのリアリティを持ってもらえる平和学習を行うことが、一番の課題だと感じている。」、渡部(わたなべ)東村山市長から、「戦争、とりわけ核戦争は最大の人権侵害である。人権教育や平和学習の中で『やはり差別はあってはならない』ということをより強調していく必要がある。」、大坪(おおつぼ)日野市長から、「平和学習の実施は、全ての基礎自治体に期待されている、党派を超えた普遍的な課題である。その推進のためには、全国的連合組織である全国市長会、全国町村会に、連携・支援いただくことが重要である。」との発言があった。

1日目は、武蔵野市の企画による「ピースフロム武蔵野」が催された。 ここでは、戦争体験を如何に次世代に伝えるかに焦点が当てられることになった。
こどもたちの素晴らしい吹奏楽から始まり、4名の戦争体験者・被爆者からのメッセージ映像「戦争の記憶を平和な未来につなげるために」が放映された。 それにより、当時市にあった有数の飛行機メーカー・中島(なかじま)製作所が9回に及ぶ空襲を受け、多くの市民の犠牲があったこと、また、戦後広島・長崎の被爆者が武蔵野市民となり「武蔵野けやき会」を結成、啓発活動を行ってきたことなどが示された。 なお、100名を超えた同会の被爆者も現在30名を切り、活動の中心は2・3世に移りつつあるとのことである。 また、写真家で、武蔵野市民の大石芳野(おおいし よしの)さんは、講演「戦禍をこえて」で、様々な地での戦争を体験された方の悲劇を、写真を通してリアルに伝えた。

戦争体験者講話を聴講(提供:武蔵野市)
その後、私から、「加盟都市の『平和に関する取組』に対する支援方策」特に若い世代への平和学習について、以下5点を説明した。
- 平和文化」と市民意識を醸成する「平和学習」は、相互に作用してスパイラルに向上するが、平和意識が極めて高かった世代が高齢化する一方で、若い世代の意識醸成が進まないと、逆に負のスパイラルが生じ、平和文化の維持が難しくなるおそれがあり、大いに危機感を持っている。
- それ故、若い世代への平和学習が、全国各地域に共通する喫緊の課題として、浮かび上がっている。
- その際、被爆地や各地の戦跡での平和学習は、平和の対極にある原爆被害や戦争をリアルに感じ取ることで、平和が当たり前ではなく、貴重なものであるとの認識変容につながり、それが大きな転換点となって、平和意識を高め、行動する契機となることが分かっている。
- このような中、広島市は、加盟都市の取組を進めるため、若い世代の平和リーダーが、広島の平和記念式典に参列し、平和学習に参加する際の派遣経費について、国の補助を受けて、助成制度を創設する考えである。
- 以上の動向を受け、2025年度の「ヒロシマ平和学習受入プログラム」の申込者は92都市、1600人超と、各加盟都市からの参加は大幅に拡大しており、また、長崎市も式典時の「青少年ピースフォーラム」への参加を積極的に勧めている。
会議での主な議論としては、主催者の小美濃(おみの)武蔵野市長から、「これからは、様々な手法を使って、若い世代に戦争についてのリアリティを持ってもらえる平和学習を行うことが、一番の課題だと感じている。」、渡部(わたなべ)東村山市長から、「戦争、とりわけ核戦争は最大の人権侵害である。人権教育や平和学習の中で『やはり差別はあってはならない』ということをより強調していく必要がある。」、大坪(おおつぼ)日野市長から、「平和学習の実施は、全ての基礎自治体に期待されている、党派を超えた普遍的な課題である。その推進のためには、全国的連合組織である全国市長会、全国町村会に、連携・支援いただくことが重要である。」との発言があった。

総会の様子(提供:武蔵野市)
また、会長である松井(まつい)広島市長からは、「行政的に平和に取り組んでいく契機となった。平和をつくるための学習を日本中で取り組む出発点の年にしたい。」との発言があった。